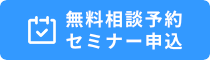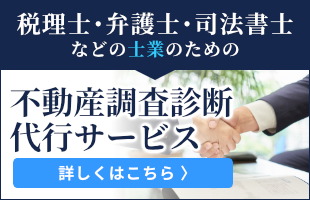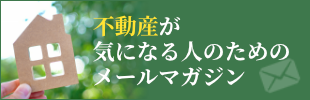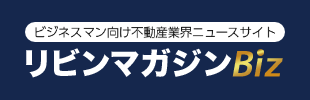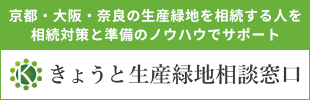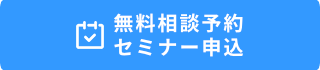- ホーム
- スマート・ホームの想い
- 相続のキーパーツ「不動産」
- スマート・ホームが考える幸せ不動産相続3つのコツ
- 相続不動産の分け方対策のコツ
相続不動産の分け方対策のコツ
不動産を次の世代に引き継ぐ際の分け方は、大きく3種類あります。
-
1.誰かが使う(住む) 
使う人の名義にするが、不公平を無くすため使う人から使わない人にお金を支払うなどするパータン。
誰の名義にするか、不公平感を無くすためのお金の計算で揉めやすいです。
-
2.物理的に分ける(土地を分割する) 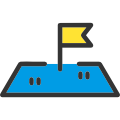
例えば、更地を2分割することで一つの不動産を二人に分けられます。
しかし土地の形状(間口が狭い)や面積(狭い)、建物がある等の理由で分割できない場合も多く揉めやすいです。
-
3.売却してお金で分ける 
3種類の方法の中で一番分けやすい。しかし、売りたくない人がいると売却できないのが難点。
また、誰の手配でいくらで売却するかで揉めることも多い。
では、相続される子供たち孫たちがずっと笑顔でいられる不動産の分け方ってあるのでしょうか?
結論から言うと、一族のみんなが必ず満足できる分け方は存在しませんので、ケースバイケースでの対応が求められます。
なぜなら、上記の3種類の分け方にはメリット・デメリットがあり、不動産の立地、規模、種類、ご家族の状況がそれぞれ異なるからです。
一族幸せになるための「不動産の分け方の対策」のコツは?
方法(テクニック)よりも「どうしたら、ずっとみんなが笑顔でいられるか?」という考え方やバランス感覚が大事です。
では、一族がずっと笑顔でいられるバランスの良い考え方とはどのようなものでしょうか。
不動産を築き上げた人(所有者)の意思を優先し、不公平を恐れないこと
大切な不動産を誰にどう使って欲しいかという、不動産所有者の希望がある場合は、その意思を優先しましょう。
相続の際に相続する人がもらえる割合(法定相続分という)が法律で定められています。
相続する人が3人の子供たちの場合、もらえる権利は3分の1ずつ平等となります。
法律で分け方の割合が決まっていても、所有者の意思を優先しても法律的に問題ありません。
同居の長男に不動産を譲る。ということも可能です。
法律による分け方の割合の定めは、相続時の話し合いがまとまらず、裁判所のお世話になる際に適用されるもので、所有者の意思を「遺言書」で指定しておくと、遺言書の分け方が優先されます。
法定相続分以外の分け方をする予定があれば、必ず「遺言書」を作成しておきましょう。
法定相続分以外にも必ず相続できる権利(遺留分という)が法律で定められていますが、所有者の意思を相続する人みんなに説明して、納得してもらえる場合、必要以上に不公平な分け方を恐れないことも必要です。
相続する人の状況に合わせたバランス感覚を
子供たちの経済状況や身体は調子の良い人、悪い人がいます。
お金に不自由していない人と生まれつき身体が弱く定職に就けない人がいたら、後者の身体の弱い人に多くの財産を遺すというバランス感覚が大切です。
不動産が一つで、分ける人が複数の場合はお金で分ける
一つの不動産を複数に分けるのは難しいです。
複数の名義(共有という)にすることは可能ですが、共有した人の同意が無いと使用や処分を自由にできないので、おすすめしません。
だれか一人の名義にするともらえない人とのバランスが悪く、人間関係まで影響が出そうな時は、不動産を売却してお金で分けた方が良いケースがあります。